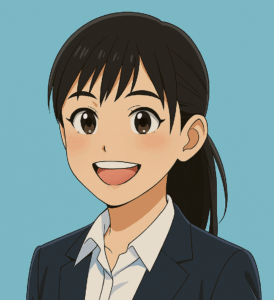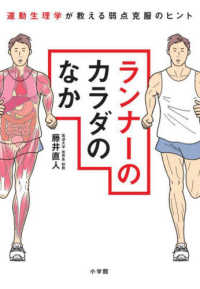第31回手賀沼エコマラソン(2025年10月)
記録
ハーフマラソン 1時間30分6秒(グロス)、1時間29分17秒(ネット)
全体順位 494位/5560人中
日時と天候
2025年10月26日(日) 10時00分スタート
気温 17℃ 天気 雨
前日までの経過
前回のレース(松戸江戸川河川敷マラソン)では、目標タイムにまったく届きませんでした。その理由についてはすでに述べたとおりです。今回のレースでは、脱水とエネルギー不足に注意することにしました。
また、今回は1時間30分という目標タイムを達成したいと考えていましたので、前週の練習量は意図的に減らしました。特に前日の土曜日は雨だったため、階段昇降を20分行うだけにとどめました。なお、当日の日曜日も雨が降ることは事前にわかっていました。
当日は車で北柏駅の北側に位置する駐車場まで向かいました。この駐車場はWeb上のサービスを利用して予約しておいたものです。料金は割高で、会場からも近くはありませんが、駐車場を探し回る時間と労力を考慮すると、最初から駐車できる場所が確保されているほうが経済的であると判断しました。
もちろん、もっと会場に近い駐車場を当日になって探すことも可能です。その場合、必要以上に早く会場周辺に到着するか、通常の時間に到着した場合は駐車場を探して回ることになります。最悪の場合、駐車場探しに時間を取られてしまい、レースに影響が出るかもしれません。特に規模の大きな大会ほど、事前に予約しておくほうが賢明です。ただし、今回は雨の影響で参加を中止した方も多かったようで、会場により近い駐車場にも十分な空きがありました。
大会運営とスタート前
大会当日は雨の中での開催となりました。柏ふるさと公園内の目立つ場所には仮設トイレが多数設置されており、特に行列ができている様子はありませんでした。ただし、そこからスタート地点までは400メートル以上離れています。
私はBブロックの近くまで移動し、店舗の軒下で雨を避けながら待機していました。すると、徐々に「トイレに行っておいたほうが良いかな」と思い始めました。ちょうど大会のアナウンスで「スタート地点から右に行くとトイレがある」と言っていたので、スタートの約20分前にそのトイレへ向かいました。5分ほどで元の場所に戻ることができ、無事にスタートブロックに立つことができました。
ウォームアップと栄養補給
今回はエネルギー不足を防ぐため、ウォームアップはほとんど行いませんでした。それよりも栄養補給に重点を置きました。まず、スタートの1時間前に大きめのシュークリームを食べました。これは1時間で消化され、レース前半のエネルギーになることを想定していました。その後、スタートの10分前にはゼリードリンクを1本飲み干しました。これはその時点から消化が始まり、レース後半のエネルギーとなることを期待しての補給です。
レース
前半10kmは1kmあたり4分15秒のペースで走り、後半に余裕があればペースを上げるというプランを立てていました。今回、新たにランナー用腕時計を購入しており、これのデビュー戦でもありました。
前半(〜10km)
スタートの号砲が鳴ると、徐々にランナーが走り始めます。私はBブロックの後方に位置していたため、スタートラインまで到達するのに約1分かかりました。スタートラインを通過した際に測定を開始しようとしたところ、「本日のおすすめ」なるプログラムが提示され、それを開始してしまいました。これは所定の速度で所定の時間を走るプログラムで、レース中に使うものではありません。
一旦そのプログラムを終了し、結果を削除してから、通常のランニングプログラムを開始しました。その間にも時間と距離が経過してしまったため、正確な測定結果は得られませんでした。事前にチェックしておけば済んだことですが、完全にノーマークでした。それでも、速度がその場でわかるという点では大きなメリットがありました。
その後も混雑していたため、スピードを上げることができませんでした。測定された最初の1kmは4分22秒でしたが、徐々に速度を上げていきました。1km4分10秒を腕時計が示すまでスピードを上げても、十分な余裕がありました。やはり、前回のレースでは気温が高すぎたのだと思います。身体の冷却が間に合えば、問題はなかったのです。
10km地点までは速度を上げず、抑えて走り続けました。約4km地点で橋を渡り、北岸から南岸へ移動します。その直後の給水ポイントでは、水をコップ1杯飲みました。手賀沼の半周を走り、折り返し前に油断して速度が落ちてしまいましたが、それ以外は4分15秒を下回らずに走ることができました。9km地点の給水ポイントでは、立ち止まって、コップに3杯のスポーツドリンクを飲みました。
後半(10km〜ゴール)
残り10kmになったところで、速度を上げることにしました。これまで残しておいた心肺の余裕を捨て、呼吸が速くなっても構わないので、ランナーを追い抜いていきました。
ところが、北岸の10kmから15kmの区間にはアップダウンがありました。初めてのコースだったため、そこは考慮していませんでした。3つほどの丘を越えるイメージで、上り下りによる速度変化は負担となります。苦しくならないようギリギリのところで走り続けました。10kmのレースを走っているような感覚でした。
15kmを過ぎ、さらに速度を上げようと思った頃、1人のランナーに抜かれました。そのランナーは走りがきれいで余裕があり、そのままの速度で走り続けると感じたため、ついていくことにしました。残りは7kmですので、行けるところまで行って、苦しくなって離されてもタイムは稼げると考えました。彼についていくことで、しばらくは良いペースで走ることができました。風除けの効果もありました。ただし、1km4分5秒のペースで走り続けているうちに、徐々に苦しくなってきました。約17km地点の橋の登り坂で離されてしまいました。

その後は南岸を再び走ります。アップダウンはもうありませんので、「何とかゴールまで行けそうだ」という感覚が芽生えてきました。心拍数は160bpmを超えており、余裕はありませんでしたが、改めてフォームを整えながらゴールを目指しました。スピードを上げることも下げることもなく、そのままゴールに入りました。陸上競技場に入ってから半周走るような、最後のまどろっこしさはなく、堤防から降りてすぐにゴールという感じでした。
振り返り
心肺を酷使したわけではなく、脚も消耗しきったというところまでは追い込んでいませんでした。とはいえ、最終盤のリミッターになっていたのは脚だったと思います。喉が渇いたとか、力が入らないという感覚は今回はありませんでした。給水とエネルギー補給は問題なかったと考えています。さすがに脚の疲れはありましたが、どこかがはっきりと痛むということはありませんでした。
心拍数の謎
レース後に心拍数の推移を確認すると、前半の7km地点までは徐々に下がり、100bpm前後まで低下していました。その後、急激に160bpmまで上昇し、そのまま推移しています。もしこの心拍数の変化が事実であれば、明らかに「にこにこペース」を超えてしまっています。この状態では長時間のランニングには向かないとされています。
実際、速度を上げると決めた後からは、徐々に脚に疲労を感じるようになりました。これは人間として極めて自然な現象です。ただし、フルマラソンを走ることを考えると、この短時間・短距離で脚が疲れてしまうのは問題です。
今回は何とか目標タイムでゴールすることができましたが、自分でも気づかないうちに心拍数が急激に上昇していました。レース中に腕時計を何度も確認していましたが、見ていたのはペースだけでした。もし心拍数も確認していたら、何が起きたのかを把握できていたかもしれません。
今後の練習では、フルマラソンを見据えて「にこにこペース」の範囲に心拍数が収まっているかを確認することを最優先にします。腕時計の表示も、最も大きく見える部分を心拍数に変更しようと思います。
| 計測ポイント | スプリット | ラップ |
|---|---|---|
| Start | 00:00:49 | |
| 5km | 00:22:08 | 0:21:19 |
| 10km | 00:43:27 | 0:21:19 |
| 15km | 01:04:39 | 0:21:12 |
| 20km | 01:25:36 | 0:20:57 |
| Finish | 01:30:06 | 0:04:30 |
2025年10月31日 追記
翌週木曜日の練習で、体感と心拍数の不一致を再び確認しました。その日は、レースの疲れも抜けて特に身体が重いという感覚もありませんでした。5kmのコースのうち、2km地点の当たりで、ふと心拍数を確認すると160bpmを超えていました。呼吸はまだまだ余裕がありました。このまま長い距離を走っていけそうなペースだと思っていたのに、心拍数だけが高いのです。
そのまま走り続けながら、速度を緩めましたが、なかなか心拍数が下がりません。そもそも速いと思っていない中でさらに速度を落とそうとしているので、速度があまり変わらなかったのかも知れませんが、それで150bpmを超えていた感じです。前日は、同じコースで140台後半で結構、速度を上げているなという印象だっただけに、非常に意外でした。
思い当たるのは、体温上昇です。その日は良く晴れており、日光により身体が温められました。調べてみると、体温上昇により心拍数が上昇するときには、酸素が不足している訳ではないので、呼吸数は上昇しないらしいです。とりあえずの仮説としては、体温上昇による心拍ドリフトとしておきます。これが正しければ、これから冬になるにしたがって、このような不一致は見られなくなるはずです。
2025年11月13日 追記
レース中の心拍数の謎が解けました。結論から言うと、心拍数が7km地点まで低かったのは、正しく測定できていなかったのです。ランニング用腕時計の心拍センサーが心拍を読み取るには、基本的に肌に密着していなければなりません。それが少し離れていたときに、測定不可になればわかりやすいのですが、私の腕時計では大幅に低い値を表示してしまうことがあるようです。単純に腕時計のバンドを少しだけきつくすれば、解決できる話でした。
本レースにおいては、7km過ぎに急激に心拍数が増加したのではなく、突然、正しい値を測定できるようになったのです。すなわち、7kmよりももっと以前から心拍数は160bpmまで上昇していました。
これとは別に体温上昇による心拍ドリフトは起こっていると思います。