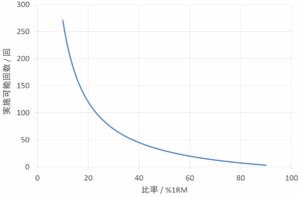キレッキレ股関節でパフォーマンスは上がる!
高岡英夫 著
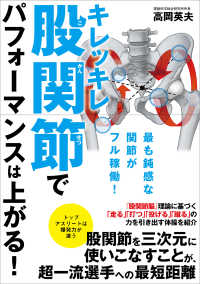
出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-EK-0704583
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★★★ 5点 |
| 理論の完成度 | ★★★★☆ 4点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★★☆ 4点 |
感想・見解
高岡英夫さんの本です。久しぶりに読みました。高岡さんは以前から、股関節や肩甲骨に着目しており、これらを動かすことで、身体の能力を引き出すことができるという主張をしています。本書は特に股関節に着目しています。股関節の位置を正しく理解することで、股関節の位置を動かすことができるようになります。そのためのエクササイズを多数載せています。
キックがうまくなる股関節の使い方
以前から、高岡さんの本は読んでいましたが、それでも、この本を読むことでいくつか新しい気づきがありました。「スポーツの場面で股関節を動かす」と題された章です。
高岡さんの洞察力はさすがです。スキーの腕前については度々言及されていますが、ボールを蹴っているという話は聞いたことがありません。しかし、キックの動作に関して、非常に精緻な描写をしています。全国のキックが飛ばないと悩んでいるキッズに読んでほしいです。
悪いキックのモデルは股関節を固定し、股関節を中心として脚を振りながら、大腿四頭筋を収縮させて膝関節を伸ばすという動きです。これだと、そもそも強いボールが蹴れない上に、ほんの少しのインパクトのズレで、ボールがゴールの遥か上方へ外れてしまいます。
一方、良いキックのモデルは、股関節自体を動かします。脚を後方に引くときには、股関節も後方に動かします。ここから、股関節を前下方に動かし、その後、上方に引き上げます。この動きの中で、股関節を前下方に動かすときに、股関節が進展します。このときに、筋肉が伸びる力を使って、より強い力を生み出す(バネ効果)と書いてあります。SSC(Stretch-Shortening Cycle)のことを指していると考えます。
最後に股関節を引き上げる動きをタイミング良く行うことで、インパクトの瞬間に地面を蹴ってしまうことを回避しながら、脚部を加速するわけです。
股関節自体を下げる動き自体は可能であると知っていましたが、キックのときは股関節を単に後方から前方へ引き付けるイメージでした。股関節を引き上げる作用は、立ち脚の膝関節を深く曲げた状態から伸展させることで実現していました。立ち脚の伸展自体はいずれにしても必要だとは思いますが、股関節自体を上下に動かすというイメージが不十分であったのかもしれません。
ランニングにも共通する対芯回旋
このようなキックの動作に関する考察が行われた後で、この股関節の動きがランニングにも共通すると、著者は論を展開します。ランニング時に右脚が離地したとしましょう。右脚は後方に跳ね上がります。左脚が着地した瞬間に右脚の股関節は左脚の股関節よりも低い状態になります。この右股関節下がりのまま右脚が前方へ運ばれていくのも、キックのときと同じです。
ここで、遊脚の股関節の方が接地脚の股関節よりも低い、という点が、私にとって驚きでした。言われてみれば、遊脚の股関節が下がっていても、膝を曲げれば、脚を前方に運ぶことはできます。実際にキックのときはそうしているのです。
その前の「股関節の動きを理解する」の章では、「股関節の対芯回旋」が股関節の活用の最高峰であるという説明がなされます。自転車の左右のペダルのように一つの軸に対して、左右が交互に回転する動きのことだと書かれています。そう言われたら、頭の中でペダルをイメージします。自転車のペダルですから、右も左も前回りだと思いますよね。私はそのように理解しました。
しかし、次の「スポーツの場面で股関節を動かす」の章で、遊脚の股関節は接地脚の股関節よりも低い状態で遊脚が前方へ運ばれると書いてあったわけです。何度読んでみても、そのようにしか理解できないように明確に書いてありますし、ボルト選手のイラストにおいてもそのように図解されています。ということは、股関節は自転車のペダルのように動くのですが、それらは後ろに回転するのです。
過去の経験から理解
なかなか簡単にイメージできないのではないでしょうか。自転車のペダルと車輪は前に回転することで、自転車自体が前に進むのです。人間が走るときの、足部の動きは、きれいな円運動ではないとしても、前回りです。だったら、股関節も前回りだと考えてしまいます。これが論理の限界なのでしょう。現実は、人間が組み立てる論理よりも複雑であるときが、頻繁にあります。
ただ、全く別の経験から、上記の意外な事実を私は納得しました。30代の前半、ナンバ走りというキーワードに基づいて、走り方を改善しようとしていました。甲野善紀さんの本を読んでいた頃です。甲野さんも胴部の動かし方について、様々な点に言及されています。私もそれに基づいて、胴部自体を動かすことをいろいろ試してみた中で、両肩を後ろ回しにペダルのように動かすと、脚がスムーズに動くことを経験していました。両肩と両脚が同調して動く感覚は得たのですが、その感覚は力を込めて地面を蹴るという動きの中では実現できなかったのです。そのため、お蔵入りになりました。(本来、捨てるべきは地面を蹴るという動作であったことは言うまでもありません。)
股関節の対芯回旋は後ろ回しであると理解したとき、両肩を後ろ回しにすることで、調和の取れた動きができたという経験を思い出し、「ああ、あれが正しかったのだ」と納得することができました。現在では、地面を全く蹴らない走りをしていますので、両肩の動きを取り入れることで、より滑らかに身体が動くようになりました。
重力ランニングの理論から導かれる動きを実現するために、身体をどのように使うかというのは、別の階層の議論と考えています。私はこれを身体層と呼んでいます。重力ランニングの動きはこうだと決まったとしても、実現の仕方は無限にあるのですから、議論が付きません。