最高のランニングのための科学―ケガしない走り方、歩き方
マーク・ククゼラ 著 / 近藤 隆文 訳

出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784152099846
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★★☆ 4点 |
| 理論の完成度 | ★★★★★ 5点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★☆☆ 3点 |
感想・見解
医者の書いたランニング本です。あくまでも、医者として、人々の健康を最優先に考えています。パフォーマンスのために健康を犠牲にするという考え方はありません。この点が、いわゆるアスリート出身の指導者が書いたランニング本とは、根本的に異なる点です。
ランニングフォームに関して新たな情報はありませんでしたが、その他の部分で取り入れたいと思う点がありました。
自然な走りが導く故障予防
著者は、ランニングの才能に恵まれた人物でした。若い頃は激しいトレーニングをしていましたが、例に漏れず、故障との戦いでもありました。その後、自らの試行錯誤により、故障を克服していくことになります。その過程において、既に紹介した ChiRunning を参考にしたと書いています。
一言で言えば、Born to Run 2と同じ考え方です。
「人間の脚には元々、走るための機能が備わっているが、それを現代のランニングシューズが阻害していることが故障の原因である。路面から足を保護するという最低限の機能に絞った靴(ミニマルシューズ)に履き替え、リラックスして走れば、長く速く走れるようになる。」
それがすべてです。細かいことをあれこれ書きすぎると、人によっては誤解や精神的ストレス、さらには別の故障を引き起こす可能性があるため、著者はあえて詳細なフォーム論には踏み込みません。医師としての自然な判断だと思います。心身の健康のためには、難しく考えすぎず、気楽に取り組むことが大前提です。
脂肪を味方にする
ここからが医者としての本領発揮です。非常に細かく、丁寧です。ランニングフォームに主眼を置いてランニングを研究している立場としては、その差に驚きました。
長距離を走る際、最も効率的なエネルギー源は脂肪である、という前提から話は始まります。体内の脂肪のうち、運動に利用できるのは皮下脂肪と筋肉内脂肪です。炭水化物(糖)をエネルギー源とするのは、高強度の運動には適していますが、血液や筋肉に蓄積できる糖の量は限られており、どんなに多くても20km程度走ると使い切ってしまいます。走る前に糖分を十分に摂った状態で速く走ると、糖によるエネルギー供給に依存し、マラソンでは後半の失速を招くことになります。走る前には、脂肪を摂るか、あるいは何も食べず(水分は十分に摂る)、体内の脂肪からエネルギーを引き出すよう身体を慣らすことがトレーニングであると、著者は述べています。
私は高校生の頃、サッカーのトレーニングとして早朝ランニングをしていましたが、そのときは水分と栄養補給を兼ねて、必ず牛乳を一杯飲んでから走っていました。頭では「寝起きの牛乳一杯では栄養が足りない」と思っていたのですが、毎朝、身体は快調に動いていました。それは、今思えば、このアドバイスに自然と従っていたからなのです。
レース本番前のカーボローディングは不要とされます。炭水化物の摂取自体は否定されていませんが、バランスの取れた食事をしておく程度で十分です。
そう言えば、『ランナーズ』でも、元ソフトバンクホークスの和田毅選手が登板前にカーボローディングをしていたところ、体調不良を感じるようになったという記事があったのを思い出しました。
カーボローディングは、マラソンでパフォーマンスを高める秘策の一つとして広く知られています。「身体に糖を最大限に蓄える」という理屈は、糖がエネルギー源である以上、正しそうに聞こえます。私はそこまでのレベルではないので実践したことはありませんが、和田選手によれば「身体が鉛のように重く感じた」とのこと。人間が考え出した理屈が現実を正しく説明するとは限りません。むしろ、カーボローディングがパフォーマンスを低下させるのです。
これまで私はランニング前の栄養補給として糖分を含むものを摂っていましたが、今後は低GI食品、あるいは給水のみで走ることに切り替えようと思います。
「速さ」より「継続」
もう一つ、非常に印象に残った指摘があります。それは、トレーニング時の速度についてです。
- 強度の高い運動をすると、回復が間に合わず故障する。故障せずにトレーニングを継続することこそが、記録を伸ばす最短ルートである。
- 低強度の運動なら、脂肪からのエネルギー供給でまかなうことができる。この状態を継続することで、脂肪からのエネルギー供給で走る速度を徐々に上げることができる。
以上を踏まえて、鼻呼吸で走れる速度がトレーニングの最適な強度だと著者は述べています。「苦しさに耐えて、高強度のトレーニングを乗り越えるほど強くなる」というのは、神話に過ぎないと断じています。
これを聞いて、また古い記憶がよみがえりました。高校生の頃に何かのマンガで、主人公がLSDに取り組む場面がありました。言うまでもなく、Long Slow Distance の略です。
当時の説明では、「長時間心拍数の高い状態を維持することで、身体の毛細血管まで血液が通るようになる」とされていました。それを聞いて、私は「常にできるだけ速く走るべきだ」という思い込みから抜け出せたのです。当時、1日4kmのランニングを日課にしていましたが、それ以降は「リラックスして流す」程度のペースに変えました。確かに、それを機に長距離を走ることが苦ではなくなり、心肺機能も高まってきたように思います。
鉄則を守らないとどうなるか
これらに反すると、大変なことになると著者は言います。糖の代謝に頼って速く走ろうとトレーニングを重ねると、エネルギー不足で失速します。これを補おうとして、さらに速く走ると故障します。故障で休むと、それを取り返そうとして、さらに強度の高い練習を行なおうとして、また故障します。著者は、自身の経験から、この状況を「ブラックホール」と呼びます。全ての努力が吸い込まれて、無に帰す、という比喩表現です。
まとめ
本書では漠然と「心肺機能を高める」ことにとどまらず、マラソンという長距離を走り切るための戦略として、ゆっくり走ることの効果を理解しました。
今のところ20kmまでは無理なく走れますが、その倍を走ろうとしたら明らかに無理がありました。この本に出合っていなければ、ハーフからフルへの移行においてブラックホールに捕らわれていた可能性は十分にあります。今回学んだことが、42.195kmを走り切る人たちの秘密かもしれません。これから試してみようと思います。


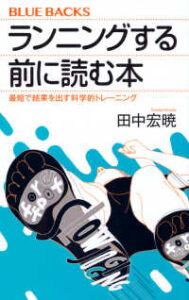
“最高のランニングのための科学―ケガしない走り方、歩き方” に対して2件のコメントがあります。