ランニングする前に読む本―最短で結果を出す科学的トレーニング
田中 宏暁 著

出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784065020050
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★★☆ 4点 |
| 理論の完成度 | ★★★★★ 5点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★★☆ 4点 |
感想・見解
本書は、『最高のランニングのための科学』と基本的に同じ内容を扱っています。ただし、本書は研究者の視点で書かれており、数々の研究結果をもとにスローランニングの有効性を解説する構成です。確かに、ブルーバックスから出版されているだけの価値があります。
これまでに紹介されてきたランニング本では、一般ランナーがトレーニング中に故障を抱えてしまうことが課題として扱われ、それを解決するためにさまざまなアプローチが提案されてきました。本書でも、第0章において「走ると故障してしまう人」が想定読者の一部として含まれていますが、それに対する具体的な解決策はフォアフット走法の提案のみにとどまっており、本書の中心的なテーマではないことがわかります。メインの読者層は、タイトルが示す通りランニング初心者です。しかしながら、ランニング歴が長く、伸び悩んでいる人にとっても役立つ知識が多く含まれています。
にこにこペースとその健康効果
本書ではまず、「にこにこペース」という概念が定義されます。これは、乳酸閾値付近――すなわち乳酸濃度が高まり始める直前の運動強度――に相当します。このペースであれば、乳酸が蓄積せず疲労がたまりにくいため、長時間走り続けることが可能です。そのため、にこにこペースで走ることができれば、マラソンの距離(42.195km)を走り切ることができるとされています。なお、乳酸閾値は最大酸素摂取量(VO₂max)によって決定されます。
さらに本書では、スローランニングがもたらす生理的な効果に注目しています。持久力の向上だけでなく、心臓病やがんの発症リスクの低下、さらには認知機能の改善といった健康面での恩恵もあるとし、老若男女問わず誰もが取り組む価値のある運動だと主張しています。
マラソン完走のための3つの戦略
マラソンを走り切るための有効な手法として、次の3つが提示されています。
- 脂肪をエネルギー源として最大限活用すること
にこにこペースは乳酸濃度が上昇しないため、長時間にわたって持続可能な運動強度です。このとき、エネルギー供給は糖と脂肪からほぼ半々で行われます。にこにこペースでの走行を継続することで、身体が脂肪からのエネルギー供給に慣れていきます。 - 最大酸素摂取量(VO₂max)を高めること
VO₂maxは、酸素を供給する循環系の能力と、ミトコンドリアによるATP再生能力の2段階で決まります。本書では前者に関する記述は少ないものの、後者については交感神経の活性化がその機能を高めると説明されています。にこにこペースでのトレーニングでも、この効果が得られるとされています。 - 身体の能力を維持しながら体重を減らすこと
これは言うまでもなく、身体が軽ければパフォーマンスが向上するという理屈です。特に、VO₂maxを出力とし、それを体重で割ることでマラソンタイムを予測できるという考え方が紹介されており、定量的な裏付けのある指標として活用可能です。
フォームの取り扱い
一方、ランニングフォームについては詳しい解説はありません。ただし、いくつかの基本方針は示されています。ここでは、フォームを細かく修正するのではなく、誤った走り方を避けるための大まかな方向性のみが示されており、長時間の実践を通して自然にフォームが整っていくという考えに立脚しています。つまり、本書ではマラソンのタイム短縮において、フォーム改善は主な要素として扱われていません。その点で、フォーム重視の「重力ランニング」とは補完的な関係にあります。
フォームに関して示されている具体例としては、まずフォアフット着地が推奨されています。また、ピッチは15秒間で45歩、すなわち1分あたり180歩以上とし、あごはやや上げる姿勢を保つことが勧められています。「地面を蹴らない」という表現も登場しますが、これは「必要以上に跳ねない」という意味合いであり、ランニングをジャンプの連続動作としてとらえていることがうかがえます。なお、フォームに関する記述はすべて文章での説明にとどまり、図表はありません。著者の研究対象が、生理学的視点から人間の身体に対するランニングの影響であることが明確に示されています。
にこにこペースで初めて見えるフルマラソンの世界
どんなに速いランナーであっても、マラソンには2時間以上の時間を要します。したがって、彼らが走る速度は少なくとも2時間以上持続可能な運動強度である必要があります。1kmを3分で走る人たちにとっては、その速度がにこにこペースであるという前提があって初めて、エリートランナーのレースが成立するのです。人間である以上、主観的に非常につらいと感じる運動を2時間以上継続することは困難であり、その点では私のような市民ランナーと変わらないのだと実感します。むしろ、「1km3分」という圧倒的なスピードが彼らにとってのにこにこペースであるという事実に、あらためて驚かされます。
このように、「42kmを走り切れる速度とは、にこにこペースでしかない」という事実を理解したとき、私はようやくハーフマラソンとフルマラソンの間に存在する不連続性の意味に気づかされました。実際、2025年3月まで、私は10kmのレースしか経験がありませんでした。その距離では、「がんばりペース」で心肺機能や体内のグリコーゲンを最大限に活用し、ベストタイムを出すことがセオリーでした。
2025年4月のかすみがうらマラソンでは10マイル(16km)を走りましたが、そのときも私は10kmの延長線上の感覚で走っていました。トレーニングでも、がんばりペースで16kmを走ることを続けていたのです。本番ではエネルギー切れにはなりませんでしたが、このままで42kmを走り切れるわけがない、ということは自覚していました。
これから本格的にフルマラソンを目指すのであれば、がんばりペースではなく、にこにこペースでのトレーニングが不可欠です。私はずっと、フルマラソンを走ることの「つらさ」を想像していました。長時間走り続ける苦行のようなイメージです。確かに、がんばりペースで42kmを走るのは苦行以外の何物でもありません。しかし、それは普通の人間には不可能です。だからこそ、実際のランナーたちは、にこにこペースまで落として走っているのです。それを無視して速く走ろうとすれば、途中で失速するのは必然なのです。この点を肝に銘じて、トレーニングに臨みたいと思います。


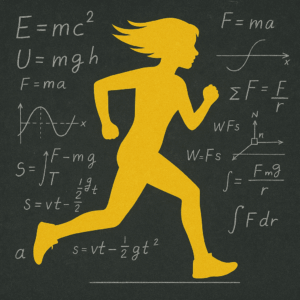
“ランニングする前に読む本―最短で結果を出す科学的トレーニング” に対して6件のコメントがあります。