マラソンは3つのステップで3時間を切れる!―運動経験のない50歳のおじさんがたった半年で2時間59分
白方 健一 著
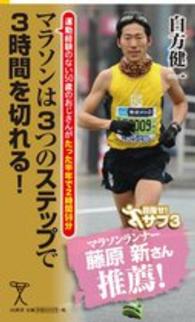
出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784797375404
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★★☆ 4点 |
| 理論の完成度 | ★★★★★ 5点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★☆☆ 3点 |
感想・見解
サブスリーを実現するために、実践的な練習方法を指南してくれる本です。内容は例によって、レース前3か月間の練習メニューがメインです。
マラソンは技術よりも論理と再現性がものを言う
私にとって強く印象に残った一文が15ページ中盤にあります。「マラソンというスポーツは、他のスポーツに比べて、“テクニックが占める割合が低い”という特徴があります。」と言い切っているのです。著者自らが主戦場としている競技を貶めているようにさえ聞こえる一文ですが、これまで読んだ本にこの一文は明記されておらず、暗黙の了解のままでした。この一文で「技術的な解説はしませんよ」と読者に対して潔く宣言しているのです。著者が非常に論理的な整合性を重んじる人であることが伺えます。
この一文の示す事柄について、私はその通りだと思います。私はずっとサッカーをしてきた人間ですが、サッカープレイヤーの共通の観念として、マラソンは「前方にまっすぐ走るだけ」の競技です。ボールと関わっていなかったとしても、サッカープレイヤーは試合中に急加速、急減速、急旋回を行うだけでなく、そもそも身体の前方だけでなく全方位に向けて走ります。その意味で、「走る」というだけでも、様々な技術が必要とされます。そこにボールが加わり、味方プレイヤーと敵プレイヤーが加わってきます。ゆえに、サッカープレイヤーにとってランニングは、自分の可能な動作のうち、ただ前方にまっすぐ走る動作だけを延々と続けるものと理解されます。元浦和レッズの柏木陽介選手は「素走り」という言葉を使っていました。
技術の要素が低いため、メンタルとフィジカルの要素が大きな割合を占めるとも書かれています。つまり、この二者の重要性を示すための一文でもあるのです。技術の要素が少ないということは、いかにセンスがあっても乗り越えられない壁があるということです。メンタルとフィジカルを作り上げるためには、少なくとも一定期間の継続的な努力が必要です。
そして、「本番レースは練習の再現である」とも言っています。この一文は、サッカーでも真なのですが、意味するところが全く異なります。サッカーでは、練習してきたことの8割も再現できれば満点です。相手の出方次第で準備してきたことの半分も実現できずに終わることもよくあります。一方、マラソンでは、練習で走ったタイムとほぼ同じタイムで本番コースをもう一度走る、という意味なのです。それくらい、準備してきたことと結果が直結するわけです。著者のように論理的整合性を求める人にとっては、そこがマラソンの魅力なのではないでしょうか。
スピード持久力の本質
フィジカルのトレーニングに関しては、「スピード持久力」と「最大酸素摂取量(VO₂max)」という2本柱です。後者に関しては、すでに「ランニングする前に読む本」の記事で触れているので、前者について取り上げます。
スピード持久力とは、文字通り、スピードを持続する力です。すなわち、レース速度をレース時間に渡って継続する能力です。これを鍛えるためには、レース速度を上回る速度でトレーニングをするのが効果的です。本書の練習メニューの中にも、必ずいわゆるスピード練習が組み込まれています。スピード練習と聞くと「苦しい」と連想するかもしれませんが、心拍数を指標にして、どの程度まで追い込めば十分であるかを示しています。逆に、限界まで追い込むことでフォームが崩れたり、身体に過度の疲労が残ったりすることを否定しています。
42.195kmを目標のゴールタイムで走り切るためには、レース速度(42.195km ÷ ゴールタイム)の負荷がLT値以下であることが前提ですが、LT値以下の運動強度であっても筋疲労は起こります。LT値以下なら無限に走り続けられるわけではないことは、誰もが知っている通りです。筋疲労は以下の要因により、筋肉が収縮・伸長を繰り返す条件から逸脱することで起こります。
- 糖の枯渇
- 水分の不足
- イオンの不足
- 中枢神経の疲労
- 体温上昇
- 代謝副産物の蓄積
これらをきっかけとしてフォームが崩れてくると、ランニングの効率が低下して疲労が拡大することになります。よって、疲労前、あるいは、疲労の初期段階でフォームを意識的に正すことができる能力、すなわちフォームを深く理解していることが有効です。ここが、マラソンにおける技術的要素の登場する場面だと考えられます。スピード持久力とは、上記の要因を全て踏まえた上で、レース速度を維持できる能力と言えるでしょう。フォームの最適化と物理的理解は、スピード持久力を構成する重要な要素の1つ、ということです。マラソンにおいて、重力ランニングの理論はこの点に貢献するのです。
スピード強化の重要性
著者が殊さらにスピードを強調するのは、「距離は速度の代わりにならない」ということを意味しています。どんなに長く(ゆっくり)走っても、速く走らなければ、速く走れるようにはなりません。仕事(単位:J)は「仕事率(W)×時間(s)」の関係式が成り立ちます。ゆっくりでも長い時間走れば、短い時間で速く走るのと同じ仕事になると考えるのは理解できます。ここから類推して、ゆっくりでも長く走ることで速く走れるようになるという誤解が生まれるのでしょう。
仕事はいわば“電池の容量”です。したがって、ゆっくりでも長い距離を走るというトレーニングは、42.195kmという距離を走り切ることをより確実にする効果はあります。ゆえに、フルマラソンを完走することを目標とする初心者にとっては、スピードは脇に置いて距離を指標とするのは、正しいと考えます。
しかし、電池の容量が十分あっても、モーターが小さいままでは仕事率は大きくなりません。サブスリーを目指すランナーは、距離ではなく、スピードを高めるトレーニングをしなければならないのです。本書では、確実に目標タイムを達成することを重視しています。ゆえに、努力しているが実らないという状況を避けるべく、この点が明記されているのです。



“マラソンは3つのステップで3時間を切れる!―運動経験のない50歳のおじさんがたった半年で2時間59分” に対して1件のコメントがあります。