型破りマラソン攻略法―必ず自己ベストを更新できる!
岩本 能史 著

出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784022736048
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★☆☆ 3点 |
| 理論の完成度 | ★★★☆☆ 3点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★☆☆ 3点 |
感想・見解
著者の認識としては「非常識のマラソンメソッド」とのことですが、読んでみた限り、さほど型破りとは思いませんでした。出版されたのは2015年ですから、その当時においても、非常識というほどのものではないと思います。フォームに関する理論は粗いという印象ですが、実直に努力を重ねることの必要性を正面から説いており、タイトルとは反対に、奇を衒わない王道を行くようなランニング本です。
以下が主たる項目です。
- マラソンは食べるスポーツである
- 膝が痛い人は薄底のランニングシューズを試してみる
- 30km走のトレーニングを過信してはいけない
- カーボローディングは無理に行わない
- 速くなるのにLSDトレーニングは逆効果
- ランナーにストレッチは不要である
- 「峠走」と「15kmのビルドアップ走」で速くなれる
実際には、著者の最大の功績は、7番目の項目に挙げられている、マラソンで目標タイムを実現するために強い相関性のある予行演習と本番タイムを見出したことでしょう。数多くのランナーに対して指導した経験のおかげで、統計的に有意と言えるだけのデータを持っているため、説得力があります。逆の言い方をするならば、予行演習で実現できなかった場合には、本番でも目標タイムを実現できない可能性が高いということです。本番の気合で何とかなることはないと、未経験者の希望的観測を事前に打ち砕いてくれます。マラソンは結果の予測可能性が非常に高い競技であると改めて感じました。
15kmのビルドアップ走
著者のコミュニティの中では、このビルドアップ走を「ソツケン」と呼ぶそうです。サブスリーの場合は、最初の5kmを21分15秒(1km4分15秒)、次の5kmを20分15秒(1km4分3秒)、最後の5kmは18分45秒(1km3分45秒)となります。
実際、自分に当てはめてみると、最後の5kmが18分45秒ということですから、私のベストタイムとほぼ同じです。それを、10kmを走った後に休みを入れずに実現しろというのですから、現状では率直に無理があると感じます。したがって、それをできる人が「サブスリーで走る人だよ」と言われたら納得します。現状の自分よりは、一段か二段上のレベルなのだと理解します。
フルマラソンを走る能力を短い距離に落とし込んだらどうなるのかは誰しも考えたことがあると思います。フルマラソンはおろか、30kmも走ったことがない自分にとって、実感できる指標でした。練習時間も限られているので、やたらと長い距離を走ることはできません。したがって、このようにフルマラソンのゴールタイムと相関性が確かめられた短い距離の指標を提示してもらえるのは、一市民ランナーにとって大変ありがたいことです。上記のソツケンをクリアできなければサブスリーは達成できないと認識しましたので、まずはソツケンをクリアできるように練習します。
ラン反射
この本には「ラン反射」という言葉が頻出します。無論、一般的な用語ではありません。明示的に定義付けされていません。具体的な動作としては2つあります。まず、離地する瞬間にアキレス腱が収縮して、地面を蹴る作用。もう1つは、着地の際に大腿四頭筋の収縮により身体を支える作用です。これら2つに対して「ラン反射」という用語を当てているので、ランニングを行うときに発生する不随意(意識されない)の動作という広い意味なのだと思います。
地面を蹴る作用については、著者はアキレス腱の収縮により不随意ながら地面を蹴っていると認識しています。この蹴るという動作を意識的に行うと疲れる、しかし、不随意(ラン反射)なら疲れない、というロジックでした。再三の指摘ではありますが、蹴る動作を「ラン反射」に委ねるという指導をすることで、本来不要である地面を蹴る動作を抑制する効果があるのです。蹴らないことで身体の上下動が小さくなり、エネルギーの無駄が減ります。随意・不随意の話ではなく、シンプルに「実際に蹴らなくなるから疲れない」のです。
フォーム
第2章ではフォームについて解説しています。マラソンに関する本としては、フォームに関する記述は多い方だと思います。著者は自分の見出した正しい走り方を想定し、そこへ導くようにアドバイスしています。
肩甲骨を寄せて骨盤を前傾させる
一般的によく言われていることです。「胸を張る」とも言われます。肩甲骨と骨盤のポジションについてこのような言い方をすると、指定されているように聞こえて上半身の動きが抑制されるかもしれません。猫背にならないようにすれば十分なので、身体の部位について個別に言及するのは控えた方が良いでしょう。
体の真下に着地する(つま先か踵かは問わない)
細かく言えば指摘したい点はありますが、基本方針として身体重心の直下を目指すという考え方は正しいと考えます。
腕振りは横に
上半身を捻ることで、反作用で骨盤が回転します。これによってストライドが大きくなり、速く走れるという理論です。
足は円形に動く(接地は一瞬)
車輪を想定していると思われます。走っているときの身体を横から見て、足が円を描くように動けばスムーズに走れそうですよね。でも、本当にそうでしょうか。車輪は円形ですから、どんな角度でも荷重を支えることができます。しかし、足は円周上の一点にしか存在しません。もし文字通りに円を描くように動かしたら走れませんし、それを目指すことも違います。主観と客観の違いを理解していないアドバイスだと考えます。文字通りに受け取るのは避けた方が良いでしょう。
X軸で走る(一直線上を走る)
要は、右足と左足が一直線上を走るか、別の軌道を辿るかという論点です。過去の動画を見てみたところ、野口みずきさんは一直線上を走るように見えますが、尾崎好美さんはそうではありませんでした。一旦、野口さんの走り方を目指すとしましょう。その場合「X軸で走る」という方針は目的にかなっていると言えるでしょう。しかし、現実には高橋尚子さんのように2軸で走る五輪の金メダリストもいるので、人それぞれと考えるのが妥当です。
ピッチ走法よりもストライド走法が良い
1つの論文を参考にこの結論を導いています。導いたというより、自身の信じる方針をサポートするために論文を引用したということでしょう。既述の腕の横振りや一直線上の着地は、ストライドを大きくするための手法として紹介されているわけです。

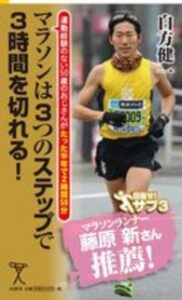
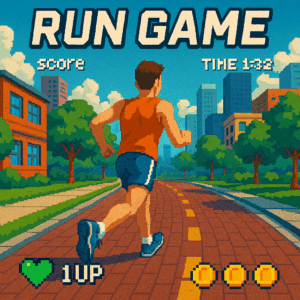
“型破りマラソン攻略法―必ず自己ベストを更新できる!” に対して1件のコメントがあります。