毎日長い距離を走らなくてもマラソンは速くなる!―月間たった80kmで2時間46分!超効率的トレーニング法
吉岡 利貢 著

出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784797364415
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★☆☆ 3点 |
| 理論の完成度 | ★★★☆☆ 3点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★☆☆ 3点 |
感想・見解
著者は研究者であり、ランナーです。
主旨は以下の2点です。
- 走る距離の一部を自転車などの他の運動に切り替えることで、ケガのリスクを抑えたまま、心肺能力を高めることができる。
- 強度の高い練習をしなければ、「筋力」「バネ」は向上しない。
距離信仰に対するアンチテーゼと言った趣です。一般ランナーでは、それほどまでに距離信仰が根深いのでしょうか。研究者がわざわざ、ランニングの一部を他の運動に置き換えてみて、トレーニングの効果は変わらないということを検証してみせなければならないほどなのでしょう。月間80kmで結果を出したとのことでしたが、クロストレーニングの分は距離のカウントに入れていない数字でした。準備にかける時間と労力という意味では、ほぼ変わらないか、設備や環境を変える手間が発生しますので「超効率的」という表現は、意外なワーディングだと感じました。
ランニングに対する認識
気になったのは、ランニングを連続跳躍だと捉えている点です。SSCによって人間は落下の運動エネルギーを上昇の運動エネルギーに変換できるという理論が正しいという前提で説明されています。そして、接地時間は短い方が、上記エネルギーの損失がなく、再変換できるから、ランニングエコノミー的に有利であると述べています。「短い接地時間でより高く跳べるランナーほどランニングエコノミーが高い」という結果が出ているそうです。しかし、この論文はリバウンドジャンプの効率をもとに話をしています。ランニングが連続ジャンプと捉え、リバウンドジャンプと同じ要領で、地面に足を強く突き、短時間で再びジャンプするのであれば、当然、リバウンドジャンプの効率が良い人はランニングのそれも良くなるでしょう。
もし、ランニングを連続跳躍であると見なしているなら、ランニング時に脚にかかる負荷は自転車の比ではありません。月間の走行距離を意識的に抑えなければ、故障するのも当然です。多くの人は、走りをそのように捉えているようですが、それは違うというのが、このブログの見解です。
この本の主旨は良く理解しましたが、前提となるランニングの認識を変えることが、むしろ、必要かと思いました。クロストレーニングが与える身体への効果は変わりませんが、長い距離を走ると故障するから、という消去法的な採用ではなく、ランニングでは実現できない効果を得るという積極的な施策となるでしょう。
フォームに関して
フォームに関する記述は存在するものの、それほど目新しい部分もなく、重きを置いているという印象ではありません。腕振りと着地に関する記述から著者は4スタンス理論でいうところのAタイプであると推定されます。これをBタイプの人が読んで、真似をすると、パフォーマンスが落ちるか、悪くすると故障してしまいますので、ご自身の身体に問いかけてみてください。
脚の運び
股関節に着目しています。一般的には膝関節の伸展に頼っているところ、股関節を動かすべきだと説いています。「ランニングにおける正しいキックは股関節の伸展動作で地面に斜め下方向の力を加えることです。」と書いてあります。
着地
フォアフット着地を推奨しています。著者もかつては踵着地をしていたのですが、フォアフット着地に切り替えたことで、マラソン中のふくらはぎの痙攣がなくなったそうです。
腕振り
「左右の脚を交互に動かすことによって生まれた回転力(角運動量)を相殺しさえすれば良い」との考えです。腕振りは小さく、肘は90°よりも曲げ、胸の近くに手首が来ると書かれているので、4スタンス理論におけるAタイプの腕振りです。
シューズ
ここは私の考えと一致しました。経験者は練習時にはソールの薄いシューズを履き、身体を鍛え、走り方をブラッシュアップすべきです。試合のときには、結果を出すことが優先ですから、厚底シューズを履いて、脚力を温存し、結果を出せば良いのです。

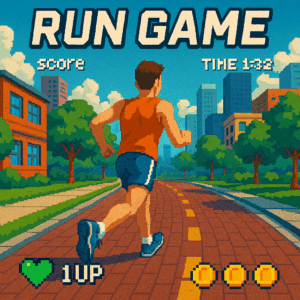
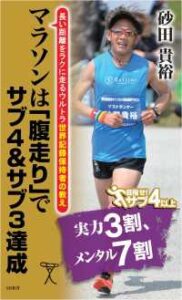
“毎日長い距離を走らなくてもマラソンは速くなる!―月間たった80kmで2時間46分!超効率的トレーニング法” に対して1件のコメントがあります。