マラソンは「腹走り」でサブ4&サブ3達成 長い距離をラクに走るウルトラ世界記録保持者の教え
砂田 貴裕 著
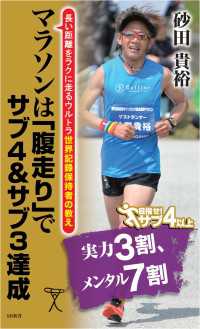
出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-9990986134
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★☆☆ 3点 |
| 理論の完成度 | ★★★☆☆ 3点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★☆☆ 3点 |
感想・見解
著者は実業団に所属したこともあるランナーです。かつての100kmのウルトラマラソンの世界記録保持者でもありますから、エリートランナーと言って差し支えありません。ある特定の走り方を推奨する本であるというのはタイトルからわかりますね。誰しも「腹走り」とはどんな走り方なのか、ということに興味を持つと思います。それ以外にも、練習メニュー、レースの準備などが含まれており、1冊でフルマラソンの教科書として機能するように構成されています。
「腹で走る」ってどういうこと?
「ランニングという運動の特性に合ったもっとも自然なランニングスタイル」と紹介されています。
「前傾を保ちながら、着地の推進力で進んでいく」とありますが、これはランニング教科書に共通する記述と言って良いでしょう。
よって、他とどう違うの?という質問に対する回答は、「お腹を意識する」ことです。重い荷物を持ち上げるときのようにお腹に力を入れる感覚を保つことで、ランニング中の体幹が安定するとのことです。以上が第一章の内容です。
フォーム・着地・腕振りまで徹底解剖
第二章ではより具体化した内容が示されます。足の運びに関しては、「足が大きな円を描いて着地の瞬間だけ1点で地面と接するイメージ」と記述しています。ダイナミックに走る方がベターという考えです。
ユニークなのは「かかとから着地して母指球に体重を乗せる」という着地を推奨している点です。昨今はそもそもフォアフット着地を推奨している本が多い中で、かかと着地を全面的に進める本は珍しいです。かかと→母指球→小趾球という順に接地していき、体重が抜けるのは小趾球からです。この感覚だと、足は進行方向に対して閉じ気味になります。
腕振りは「ヒジを後ろに引くイメージ」とのことです。さらに、「手のひらを上に向けるようにする」と肩甲骨が寄せやすくなるので、望ましいです。
「腕をできるだけ低いポジションに」するように推奨しています。身体の部位について、なかなか詳細な指示です。
総じてみると、著者は4スタンス理論におけるBタイプの走りを指導していると考えます。上記のアドバイスに従ってみて、身体が動かしやすいと感じれば、あなたもBタイプである可能性が高いです。そのまま、続けてみましょう。しかし、違和感があるならば、上記のアドバイスを採用する必要はありません。自分にあった指導者(ランニング本)をまた探しましょう。
マラソンにおける心理的要因の再評価
著者は、私から見れば走る才能に恵まれた人ですが、それでも、日本代表に名を連ねて華々しくキャリアを築いたわけではありません。実業団を退団して、1人で練習してきたというのが彼の基本的な自己理解です。それゆえか「マラソンは7割がメンタル勝負」と題された第4章では、令和の今には珍しいトレーニング方針がいくつか示されています。これを書くとリスクがあるかもしれないと感じられるような「根性論」とそれに付随する事項です。
昭和の時代に正しいとされていたことの中には、誤りもありました。それを是正していく中で、勢いが付きすぎて、逆の問題が発生していることもあると私は思います。私も昭和を生きた人間ですので「根性論」の弊害も経験しました。しかし、昭和の時代を支えた「根性論」がもたらしたのは弊害だけではなかったはずです。強くなりたいなら、根性も必要だと思います。
キツイ練習をランクラ(ランニングクラブ)に頼り過ぎない。一人で練習し、自らの身体と対話する。
仲間と競い合うと言えば、聞こえは良いですが、特にランニングという競技の特性上、他人との関係性を前提にするのではなく、自分の意志として物事に取り組むことが重要です。ランクラでの練習を否定するわけではありませんが、それだけではないということです。
決めた練習は最後までやり切る。コンディションが悪いなら悪いなりに練習を最後までやり切る。
コンディションが悪いときは必ずあります。そのときに、早々に練習メニューを変更するという考え方もあり得ると思います。しかし、ほとんどの場合、それは自分の怠け心が原因でそのように感じるだけで、実際には問題ありません。ですから、ともかくできるところまでやってみる、の精神で練習を続け、本当にコンディションが悪いとしても、最後までやり遂げるのは、尊いことだと考えます。
悪天候でも練習に出かける。
これも大事なことです。真に悪天候で走りに出かけるべきでないときは、気候変動により頻度が増していますが、そういう話ではありません。「少し雨が降っている」が止める理由になるなら、次は「風が吹いている」が理由にもなりえます。あれこれ止める理由を探さずに、問答無用で始めてみることが大事です。
あえて水分を控えてみる。
これもなかなか文章にしづらいことです。加減がわからずに、本当に熱中症になった人がクレームをつけてくるかもしれない世の中です。何らかのトラブルで水が飲めなかったときでも、諦めないでいれば乗り越えられることが大半でしょう。簡単に弱気にならないという教訓です。


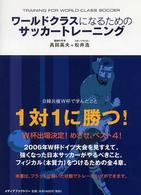
“マラソンは「腹走り」でサブ4&サブ3達成 長い距離をラクに走るウルトラ世界記録保持者の教え” に対して1件のコメントがあります。