「3時間切り請負人」が教える!マラソン“目標タイム必達”の極意
福澤 潔 著

出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784797382709
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★☆☆ 3点 |
| 理論の完成度 | ★★★★☆ 4点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★☆☆ 3点 |
感想・見解
著者は学生時代に5000mを15分30秒で走っていました。フルマラソンの自己ベストは2時間23分18秒とのことです。基準となる速度が違います。アスリートではなくとも、一般的なランナーとは明らかに一線を画す実力です。そのような著者が、これまでの指導経験を元にフルマラソンの目標タイム達成の極意を教えてくれる本です。
嫌な練習・辛い練習はしない
30km走とインターバル走は不要と言っています。著者は、高専時代の自身の経験から、無理に追い込んでも記録は伸びないと実感しているのでした。良くあるランニング本は、自己管理において十分に回復できるという前提で、30km走やインターバル走を入れることで速くなるとされています。本書では、そのような高強度のトレーニングは不要としています。唯一のそれらしき箇所として、ビルドアップ走の最後の1kmはレースペースまで上げる、と言っています。それでも、レースペースより速く走れとは言っていません。練習として体力の向上を目指すには、30km走は長すぎる。そして、インターバル走は強すぎるのです。苦しい練習をやり切った感は得られますが、それに隠れて自覚できない疲労が身体に蓄積するのです。本書の中で、繰り返し書かれていますので、本当にそう感じているのだと思います。
一方で、LSDも否定します。LSDの名のもとに低強度の練習に陥ってしまうのは、そもそも身体が疲れてしまうからです。ケガや疲れで、速く走れない状態であるにも関わらず、がんばって距離を稼ごうとするから、LSDになってしまうのです。その前段階には、分不相応に高い強度のトレーニングがあったはずです。それを30kmやインターバル走であると看破した上で、これらを否定しているのです。
オーバーワークによるデメリットを軽視するのは日本人に蔓延している傾向であると私も思います。社会全体が、客観的な成果ではなく、がんばった感を指標としてしまうのです。著者は富士フイルムに勤務しながら、競技生活を続けていたそうですが、残業が当たり前だったため、練習時間を捻出することが困難でした。そこで、通勤ランを続けていた結果、40代までほとんどベストと同じ記録でフルマラソンを走ることができたそうです。この話も、残業ありきの日本社会の問題点を間接的に指摘しているわけです。と言いつつも、著者は通勤ランを推奨しています。
上げるのではなく、上がる
ポイント練習はビルドアップ走だけと言っても過言ではない印象です。ここでポイントなのは、ビルドアップ走と言いつつも、ペースを上げるのではないということです。「上げる」のではなく「上がる」感覚と書いています。至言だと思いました。
「上げる」と考えていると、自分の出力(がんばり)の方に意識が向いてしまいます。目的は出力を「上げる」ことではなく、速度が「上がる」ことです。理想は、出力を上げなくとも、速度が「上がる」です。すなわち、体感としてがんばったつもりはないが、時計の数字は小さくなっていたというのが目指すべき状況です。
フォームに関する話
本ブログはフォームの改善を主眼とするものですから、フォームは個性という考えです。体格、スピード、持久力によって変わってくるものであるから、矯正することはしません。いくつかの基本的な事項を指摘するだけです。毒にならない程度にとどめてあると言えます。
本当にそれだけで足りるのか?
これまで紹介してきたランニング本と矛盾していると言わざるを得ない部分はあります。
LSDを否定している点は共通ですが、その結論として、強度の高い練習をしなければならないということにはならず、辛い練習はしなくて良いという話になるのは意外です。30km走もインターバル走も他の本では、ポイント練習としてしっかりと名を連ねていたはずなのに、それらを不要と断じています。距離は15kmで十分とのことです。フルマラソンのレースは負荷が高いため、それを再現するような練習は身体への悪影響が大きすぎるのです。したがって、練習における根性は不要です。ただし、レースでは我慢が必要と述べ、精神力の重要性を説いています。
「レースはトレース」という考え方もありましたが、その観点から見ると、15kmではフルマラソンの半分以下ですから、トレースするべき内容がそもそもありません。逆に、本番の高揚感から、レースでは練習よりも1キロ当たり10秒速く走れると言っています。これまでの指導経験から、完全なリハーサルが無くても、15km以降の未知の部分は乗り越えて、目標タイムを実現できるとしています。その違いの存在を認め、レース計画に含めているのです。苦しくない範囲で走ることだけで速くなれるという主張は、結局のところ、田中 宏暁氏と同じです。

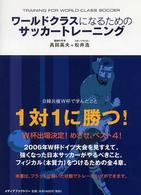
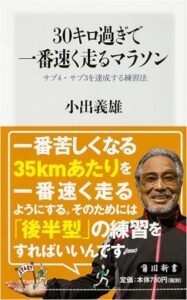
“「3時間切り請負人」が教える!マラソン“目標タイム必達”の極意” に対して2件のコメントがあります。