30キロ過ぎで一番速く走るマラソン―サブ4・サブ3を達成する練習法
小出 義雄 著
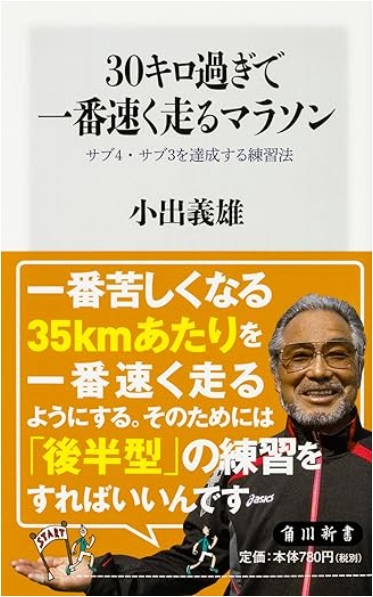
出典:https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784047316263
評価
| 項目 | スコア |
|---|---|
| 重力ランニングとの親和性 | ★★★☆☆ 3点 |
| 理論の完成度 | ★★☆☆☆ 2点 |
| 読み物としての面白さ | ★★★★☆ 4点 |
感想・見解
著者は言わずと知れた名伯楽です。私の中では、高橋尚子さんの指導者です。しかし、実際には、高橋尚子さんのシドニー五輪に先立って、有森裕子さんの2大会連続メダル獲得があったのです。
小出監督の指導は、単に厳しい(量が多い)メニューを課しているだけのように見えます。ただ、マラソンにおいては後半型のレースマネジメントという当時としては新しい方針を提示しました。
それは、生理学的知見に基づく立案ではなく、経験則だと思われます。というのは、小出監督の本には生理学的な裏付けがまったく登場しないからです。しかし、物事を思い込みを排して見極めるという姿勢は、人生において非常に重要なことです。多くのランナーが口にする「30kmの壁」と、逆に成功したランナーのレース運びを見て、シンプルに「前半は抑え気味の方が良い」という経験則を導き出したのでしょう。具体的にいつ、どこで、そのような方針を見出したのかについてはこの本では触れられていませんでしたが、そのように推測されます。
苦しい練習の意義
小出監督はアスリートに対する指導が本職です。本書の後半では一般ランナーの手記が登場しますが、彼らに対しては3か月分の練習メニューを提供したに過ぎません。アスリートは、競技において勝つことが人生の中心にある人たちです。そのような場面では、苦しい練習をするのは当然です。したがって、小出監督はアスリート指導において、当然のことを述べているに過ぎません。特に、糖代謝で走る距離(ハーフマラソン以下)については、単純に苦しさを乗り越えて走る訓練によって速くなるのではないでしょうか。もちろん、苦しければ苦しいほど良いというわけではないと思いますが、明らかに苦しいと感じる領域での練習は必要です(下表の根性派)。これがそもそも小出監督の言っていることです。
単なる鬼監督なら、そこら中にたくさんいます。しかし、そうではないからこそ、傑出したランナーを輩出しているのです。小出監督の優れている点は、マラソンにおいてその原則に例外を設けた柔軟性です。前半部分では出せるスピードを出さず、つまり苦しくない状態で走るのです。練習では、苦しさを乗り越えて走るという原則は守られていると思います。選手の様子をよく観察し、故障しないように強度や量を絶妙に調整しているのでしょう。
これに対して「苦しい練習をしなくても目標タイムを実現できる」すなわち「向上することができる」と主張する人たち(下表のLT値派)がいます。この2つは矛盾するように聞こえます。小出監督の指導は間違いなく結果を残しているのですから、その一事をもって、正しいと言えます。しかし、指導された側が結果を残すということだけであれば、今まで紹介してきた本の著者も一定の成果を挙げているわけですから、それもまた正しいということになります。
「苦しむ必要はない」とする人は、それが最も近道だと主張しますが、それはほぼ確実にケガを避けられるからです。いわば、自動車運転で最も目的地に速く到達するのは(事故の起こらない)安全運転だと言っているようなものです。それはある意味で真実です。日々自動車を運転している人であれば、よく理解できるでしょう。この主張は、それ自体として正しいのです。
小出監督は、アスリートに対して、解糖系代謝競技からの原則に修正を加えることでマラソンに対応しました。一方、田中氏は、一般人がどのようにすればマラソンに最も効率的に適応できるかを追求しました。したがって、一般ランナーのマラソンの目標タイム達成に限った場合、LT値トレーニングの方が正しいように思われます。小出監督の指導は、安全運転ではなく、事故のリスクを覚悟の上で走る、いわばカーレースのためのものだと感じました。
以下に両者の特徴を整理しました。
| 観点 | 根性派 | LT値派 |
|---|---|---|
| 主な指導対象 | アスリート | 一般ランナー |
| 練習の基本方針 | 苦しい練習を乗り越える | 苦しい練習は不要 |
| マラソン戦略 | 前半抑えて後半勝負(経験則) | 前半抑えて後半勝負(生理学的知見) |
| リスク | オーバーワークによる故障、燃え尽き症候群 | 身体能力の限界までは引き出せない |
| 例え | カーレースで最速ラップを目指す | 安全運転で目的地まで早く到達する |
| 著者 | 小出 義雄、砂田 貴裕、吉岡 利貢、岩本 能史 | 福澤 潔、田中 宏暁、マーク・ククゼラ、白方 健一 |
ハーフマラソンとフルマラソンの間には、競技の性質に根本的な違いがあると考えています。マラソンにおいて最も苦しい局面が30kmの壁にあるのは間違いありません。これを乗り越える方法については、前半を抑えるということで一致しています。エネルギー不足に陥ってしまったら、苦しさに耐えて走る訓練は役に立たず、大きくタイムを崩してしまうのです。したがって、私がマラソンという長距離に特化するのであれば、LT値で継続的にトレーニングすれば、目標タイムへ到達する最短ルートであると私は信じています。
フォームについて
一切触れていませんでした。まるで監督の仕事は練習メニュー作成だけだと言わんばかりです。行間に書いてあると言うべきでしょうか。そのメニューをこなそうとするなかで、高橋尚子さんは自分でフォームを磨いていきました。誰かが高橋尚子さんのフォームにケチをつけたとしても、一切気にすることはなく、「Qちゃんはあのままで良い」と、取り合わなかったそうです(本書ではなく、何かのテレビ番組で言っていたことです)。このエピソードから、小出監督がいかに選手の個性を尊重しながら、指導していたかが伝わってきます。


